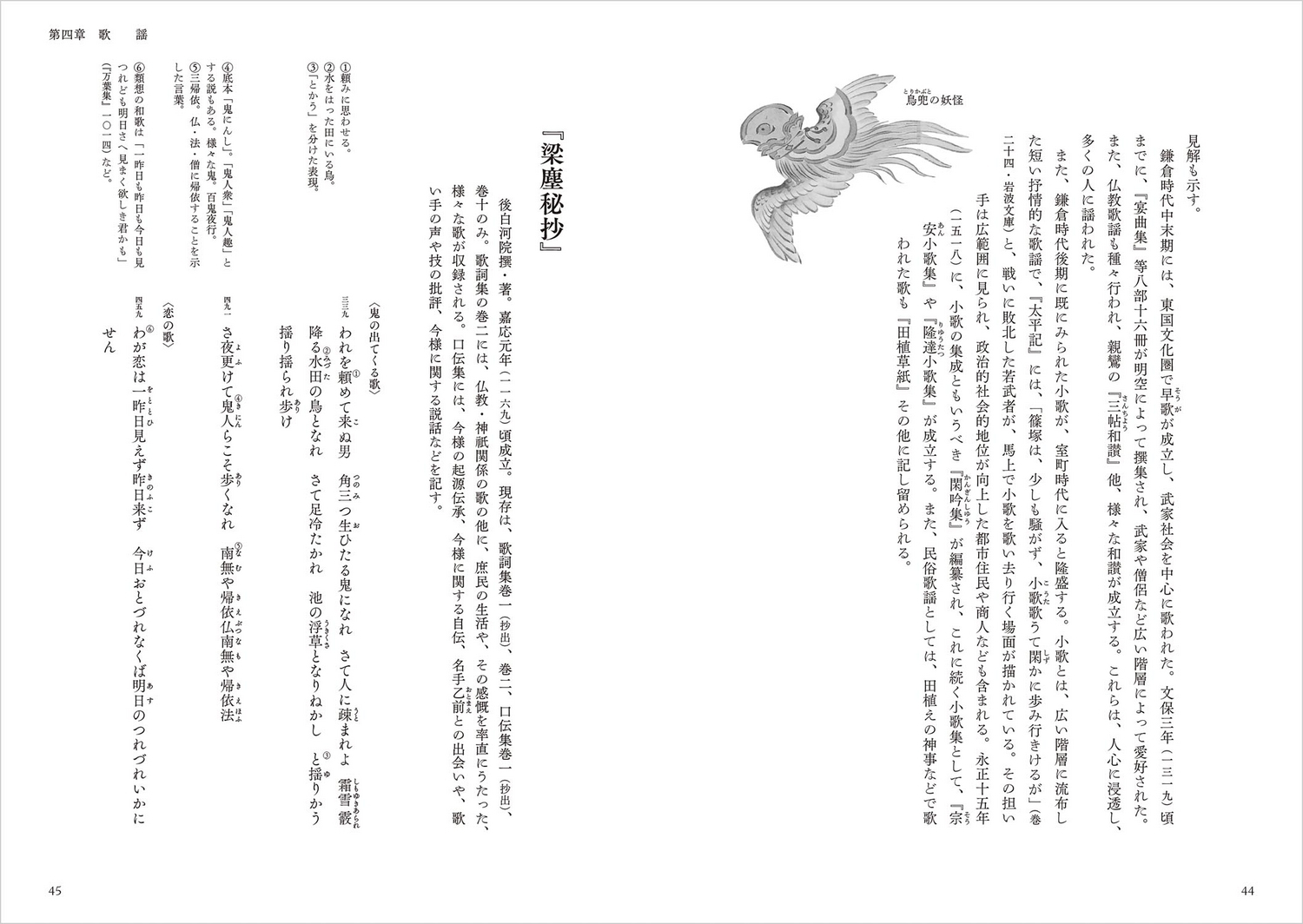2024年3月末発行(4月10日ごろ発売)の新刊を紹介します。

『百鬼夜行する中世文学:作品講読入門』
畑中智子〔代表編者〕、中前正志〔編者〕、川渕亮子〔編者〕、高重幸枝〔コラム〕、神保尚子〔イラスト〕鬼尽くしの中世文学講座。魑魅魍魎が跋扈する妖(あやかし)の世界へようこそ。
中世文学を学びたいけれど、何から始めればいいのかわからない。そんな人にぴったりの作品講読入門書。なんとテーマは「鬼」! 中世期に跳梁跋扈、大活躍した「鬼」という存在を通して、当時の人々の心情に触れ、感動や共感、涙や笑いに溢れた中世文学の魅力に迫ります。取り上げた作品の解説はもちろん、鬼にまつわるコラムや鬼出没マップ、おまけに遊べる能双六も収録。
2024年3月29日発行(4月10日ごろ発売予定) A5判・並製 186ページ
定価=本体1,600円+税 ISBN978-4-904596-14-2
【目次】
はじめに
百鬼夜行とは
第一章 和歌
『新古今和歌集』『玉葉和歌集』『風雅和歌集』『山家集』『金槐和歌集』『明日香井和歌集』『夫木和歌抄』『拾玉集』
(コラム)鬼のような悪筆
第二章 歌論
『俊頼髄脳』『古来風躰抄』『詠歌大概』『為兼卿和歌抄』
(コラム)角隠し
第三章 連歌
『水無瀬三吟百韻』『新撰菟玖波集』『新撰犬筑波集』『守武千句』
(コラム)「餓鬼となりては食にうへ」――法語
第四章 歌謡
『梁塵秘抄』『閑吟集』
(コラム)見目麗しき鬼、酒呑童子(1)
第五章 随筆
『徒然草』
(コラム)病は鬼から
第六章 歴史物語・史論書
『水鏡』『愚管抄』
(コラム)見目麗しき鬼、酒呑童子(2)
第七章 日記文学
『建礼門院右京大夫集』『とはずがたり』
(コラム)接頭語としての「鬼」
第八章 軍記物語
『平家物語』
(コラム)『伊勢物語』の鬼
第九章 中世王朝物語
『松浦宮物語』
(コラム)中国の鬼
第十章 説話
『宇治拾遺物語』『閑居友』
(コラム)女と嫉妬と鬼
第十一章 御伽草子
『一寸法師』
(コラム)鬼と祭り
第十二章 評論
『無名草子』
(コラム)鬼おにマスク
第十三章 謡曲
『野守』『風姿花伝』
(コラム)天草本『平家物語』のQicai ga xima
第十四章 狂言
『鬼のぬけがら』『鬼瓦』『節分』
(コラム)桃の木に縛られた鬼――五山文学
中世文学関連略年表
鬼鬼マップ
鬼と双六で勝負!?
担当者一覧
あとがき
鬼にテーマを絞った中世文学の入門書。作品講読というとお堅い内容だと思われがちですが、遊び心満載で楽しく学べる本になりました。
本書が並ぶお店は、来週あたりから随時烏有書林の本があるお店(リアル&ネット)に反映させていきますので、ご興味のある方はぜひチェックしてみてください。